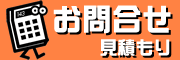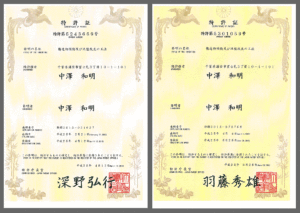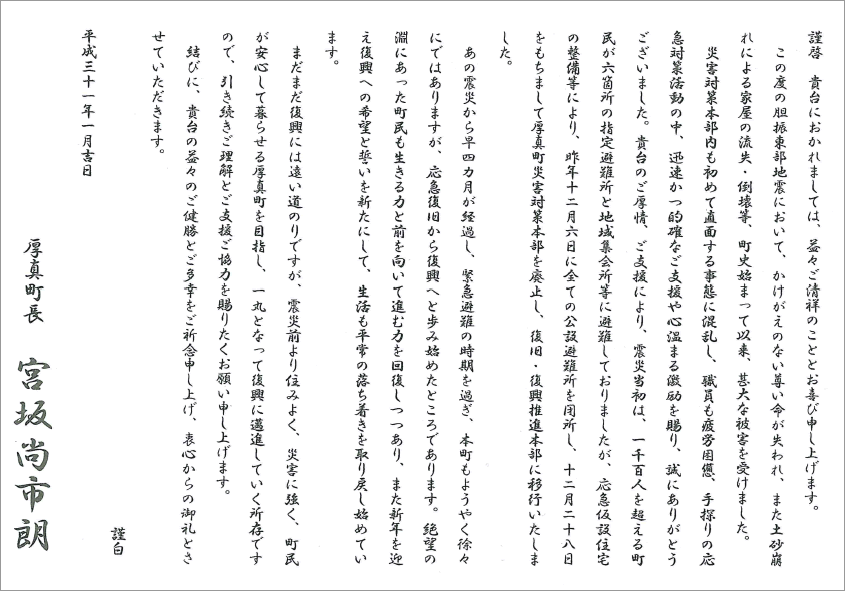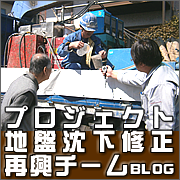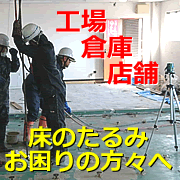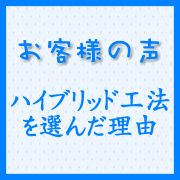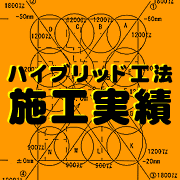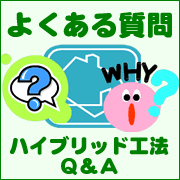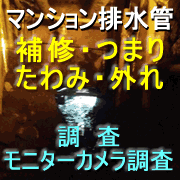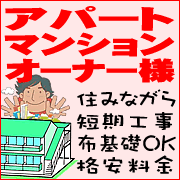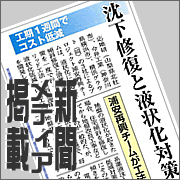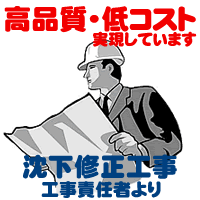建物の外側より地盤改良を行って、中央付近の地盤改良が行えるのか? -2012/03/22-

本日は以前の質問事項に加え、最近聞かれる内容についてお答えいたします。
Q. 建物の外側より地盤改良を行って、中央付近の地盤改良が行えるのか?
A.
行えます。なぜなら、比較的良好な地下6から7m(所によってはそれ以上)に存在する旧海底面(沖積層)より地盤の改良を行っており、建物の中央付近で地盤改良を行い、地盤を固化するとともに、上部の土をガンガンに締め固めております。その荷重は全周方向に約2.5kgf/cm2(25t/m2)かけております。その圧力を掛けながら徐々にロッドを引き上げておりますので明確に地盤は改良されております。その証拠に ハイブリッド工法 では、建物の中心が明確に盛り上がってきます。さらに布基礎においても中央付近の床が下がることもなく、縁の下の表土が非常に固く締まることも目視できます。建物の直下はセメント注入材が地下水を排除しながら土粒子の隙間を埋め、砂をぎゅっと締固め、飽和状態となり、行き場が無くなり、その結果として重たい漬物石のような建物が上昇せざるを得ない環境となるのです。
どれだけの地盤改良が行われているのか判りますよね。
さらに、注入されたセメント系注入材の初期強度はさほどのものではございません。
日数が経つにつれて強度が増すんです。だからより下がらない環境となるのです。
これらの内容は同業者でも、専門家でも先生でも理解できない人には判りません。だから変な事を言われるのでしょうか? 弊社とは内容自体は異なりますが、戸田建設さんの液状化対策で検索してみてください。似たような施工例はゼネコンでも検索できます。実物ならば弊社で行った布基礎の建物修正のお宅の縁の下をお見せしたいです。
この内容はあまり公言したくはありませんでした。なぜなら以前は真似されると思ったからです。しかし、弊社にて旧海底面からの注入とか建物全周の注入とか30m3以上の注入とかを明記したことにより、他社も同様にやらざるを得ない環境となりました。これが住民の方々に浸透したことは非常に効果があったと思います。
現在、弊社の工法が徐々に認知され、高い評価をされるようになりました。今やイニシアチブは弊社にあると共に、質や内容および価格において負けません。弊社は最初から建物傾き修正における技術費用や営業費用は値引きしております。それで良いと思っております。
さらに勉強不足の他社の営業マンにおかれましては、他社の工法や自社の工法についての利点や問題点などを含めてもっと本質的な勉強をすべきです。小手先の営業や知ったかぶりはだめです。特に再液状化は同じ場所では起きにくいとか言っておられた会社や営業マンはこの事業から即刻退場すべきです。住民の方々にとって非常に迷惑な存在です。
先日の余震により、神栖市内の同じ場所で再液状化が起きた事実が確認されました。
揺れの規模は先の震災の半分だそうです。その事実を重く受け止めるべきです。
さらに浦安市内の旧市街と新町では先の震災では震度が1違った事実もあります。揺れの規模は少なくとも数十倍です。縁の下を固め震度を下げる減災という行為が必要なことは明らかでしょう。一年も経つと一般住民の方々も真実がわかるでしょう。
もう一つ、プッシュアップ工法における建物土台と基礎をつなぐアンカーの切断は地震時の横揺れの際には致命的です。また、基礎の鉄筋の切断もしかりです。必ず同等以上の補強をさせると共に、専門家に相談しましょう。点付け溶接とかではダメですよ。
耐圧版工法においては地下2~3m前後に緩い地盤があることを認識させて下さい。埋戻しは土ではダメです。緩い地盤は再液状化時には致命的です。さらに再液状化で傾いた際の再修正は容易にできますか?
地盤改良併用耐圧版工法においてはジャッキポイントの本数の確認や注入量の確認を行うべきです。どちらも中途半端になる可能性があります。特に液状化対策を行うという業者は何をもって液状化対策なのかを明確にさせるべきです。注入の杭などはせん断や曲げ耐力においても何の役にもたちません。
鋼管杭施工は少なくとも沖積層に届いているのか?摩擦を設計荷重に取り入れてないかを確認すべきです。
最後に、私は自分の家がやられたら嫌だと思う、あくまで一般論を申し上げております。
他社や他工法を否定しているわけではございません。
もし、そのような工事がなされたとしても私が指摘せずとも いずれは誰かが指摘するものです。その時に大問題にならないように良く考えて工事を行う必要はありますよね。
私は全ての工法の経験がありますし、施工もできます。ただ 浦安市内ではセメント系薬液注入工法により地盤の改良を行いながらの建物傾き修正が最適 だと思っているだけなのです。
Q. 注入は何箇所から行うのですか?
A.
基本パターンは16箇所ですが、そこから位置や方向を変えて注入しています。さらに注入深さも変えていきますので 少なくとも16箇所の2~3倍の注入本数となります。
Q. 建物の外側より地盤改良を行って、中央付近の地盤改良が行えるのか?
A.
行えます。なぜなら、比較的良好な地下6から7m(所によってはそれ以上)に存在する旧海底面(沖積層)より地盤の改良を行っており、建物の中央付近で地盤改良を行い、地盤を固化するとともに、上部の土をガンガンに締め固めております。その荷重は全周方向に約2.5kgf/cm2(25t/m2)かけております。その圧力を掛けながら徐々にロッドを引き上げておりますので明確に地盤は改良されております。その証拠に ハイブリッド工法 では、建物の中心が明確に盛り上がってきます。さらに布基礎においても中央付近の床が下がることもなく、縁の下の表土が非常に固く締まることも目視できます。建物の直下はセメント注入材が地下水を排除しながら土粒子の隙間を埋め、砂をぎゅっと締固め、飽和状態となり、行き場が無くなり、その結果として重たい漬物石のような建物が上昇せざるを得ない環境となるのです。
どれだけの地盤改良が行われているのか判りますよね。
さらに、注入されたセメント系注入材の初期強度はさほどのものではございません。
日数が経つにつれて強度が増すんです。だからより下がらない環境となるのです。
これらの内容は同業者でも、専門家でも先生でも理解できない人には判りません。だから変な事を言われるのでしょうか? 弊社とは内容自体は異なりますが、戸田建設さんの液状化対策で検索してみてください。似たような施工例はゼネコンでも検索できます。実物ならば弊社で行った布基礎の建物修正のお宅の縁の下をお見せしたいです。
この内容はあまり公言したくはありませんでした。なぜなら以前は真似されると思ったからです。しかし、弊社にて旧海底面からの注入とか建物全周の注入とか30m3以上の注入とかを明記したことにより、他社も同様にやらざるを得ない環境となりました。これが住民の方々に浸透したことは非常に効果があったと思います。
現在、弊社の工法が徐々に認知され、高い評価をされるようになりました。今やイニシアチブは弊社にあると共に、質や内容および価格において負けません。弊社は最初から建物傾き修正における技術費用や営業費用は値引きしております。それで良いと思っております。
さらに勉強不足の他社の営業マンにおかれましては、他社の工法や自社の工法についての利点や問題点などを含めてもっと本質的な勉強をすべきです。小手先の営業や知ったかぶりはだめです。特に再液状化は同じ場所では起きにくいとか言っておられた会社や営業マンはこの事業から即刻退場すべきです。住民の方々にとって非常に迷惑な存在です。
先日の余震により、神栖市内の同じ場所で再液状化が起きた事実が確認されました。
揺れの規模は先の震災の半分だそうです。その事実を重く受け止めるべきです。
さらに浦安市内の旧市街と新町では先の震災では震度が1違った事実もあります。揺れの規模は少なくとも数十倍です。縁の下を固め震度を下げる減災という行為が必要なことは明らかでしょう。一年も経つと一般住民の方々も真実がわかるでしょう。
もう一つ、プッシュアップ工法における建物土台と基礎をつなぐアンカーの切断は地震時の横揺れの際には致命的です。また、基礎の鉄筋の切断もしかりです。必ず同等以上の補強をさせると共に、専門家に相談しましょう。点付け溶接とかではダメですよ。
耐圧版工法においては地下2~3m前後に緩い地盤があることを認識させて下さい。埋戻しは土ではダメです。緩い地盤は再液状化時には致命的です。さらに再液状化で傾いた際の再修正は容易にできますか?
地盤改良併用耐圧版工法においてはジャッキポイントの本数の確認や注入量の確認を行うべきです。どちらも中途半端になる可能性があります。特に液状化対策を行うという業者は何をもって液状化対策なのかを明確にさせるべきです。注入の杭などはせん断や曲げ耐力においても何の役にもたちません。
鋼管杭施工は少なくとも沖積層に届いているのか?摩擦を設計荷重に取り入れてないかを確認すべきです。
最後に、私は自分の家がやられたら嫌だと思う、あくまで一般論を申し上げております。
他社や他工法を否定しているわけではございません。
もし、そのような工事がなされたとしても私が指摘せずとも いずれは誰かが指摘するものです。その時に大問題にならないように良く考えて工事を行う必要はありますよね。
私は全ての工法の経験がありますし、施工もできます。ただ 浦安市内ではセメント系薬液注入工法により地盤の改良を行いながらの建物傾き修正が最適 だと思っているだけなのです。
Q. 注入は何箇所から行うのですか?
A.
基本パターンは16箇所ですが、そこから位置や方向を変えて注入しています。さらに注入深さも変えていきますので 少なくとも16箇所の2~3倍の注入本数となります。