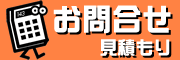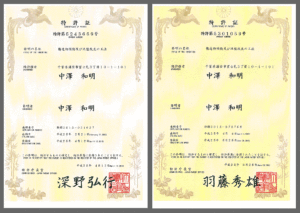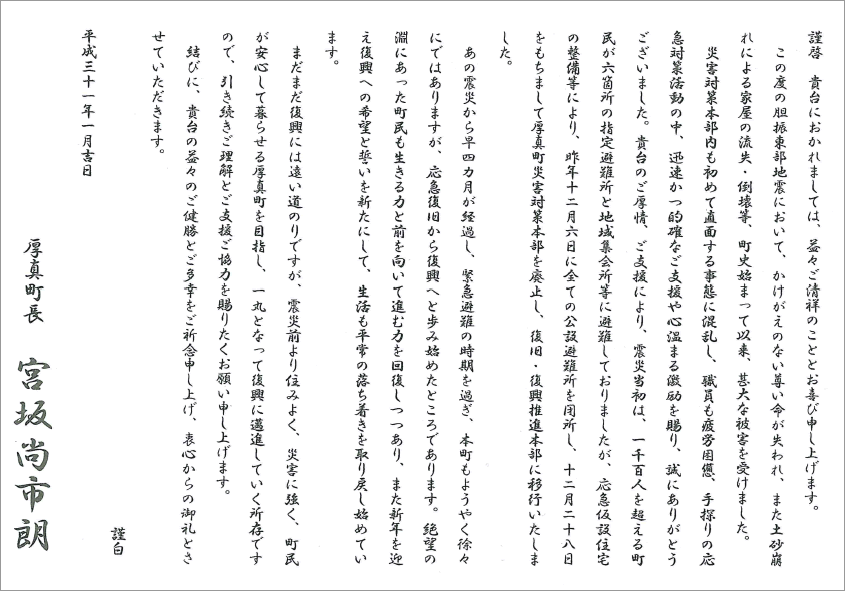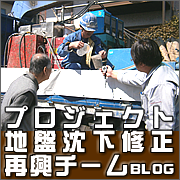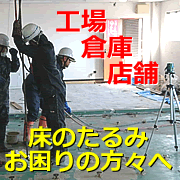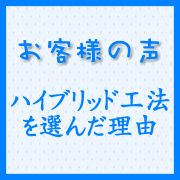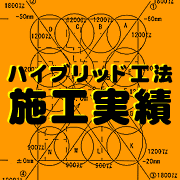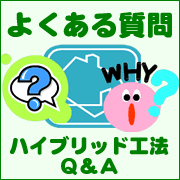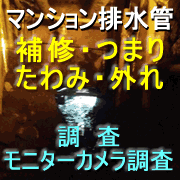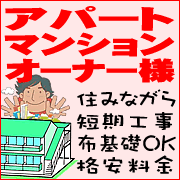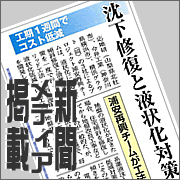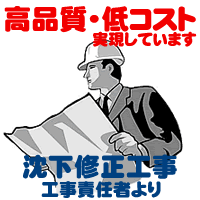地盤工学会の論文を一読して -2012/08/06-

7月に八戸にて開催された地盤工学研究発表会の資料を拝見させていただきました。
全てでは無いですが、様々な論文から既存建物がある場合の液状化対策における有用な手段をざっとまとめてみると
① セメント系薬液注入(先の2度に渡る中越沖地震においても効果が確認されている。)
② 3m厚程度の表層改良
③ 地下水位低下工法(セメント系薬液注入または3m厚程度の表層改良との併用)
現在の技術で対応が可能と思われるものは以上のようなものとなります。(他にもあると思いますが) 私が昨年より申し上げている内容が、第三者により、理論や解析結果や事実として発表されております。
① セメント系薬液注入
対象地盤の体積比7%以上の注入により、水の流れやすさを1/10~1/100にすることができる。(液状化に伴う、噴水や噴砂量を劇的に改善することが可能)
主な理由: 浸透しにくい材料の使用、土粒子の骨格の変化、密度の増加等による
② 3m厚程度の表層改良(レベル1程度の地震の場合)
表層3m程度の非液状化層の形成により、その下で液状化しても地上に影響を与えにくい。
被害の大きい家屋ほど、表層の盛土に山砂分が多い土を用いている場合が多い。
(舞浜3丁目、弁天1丁目、美浜3丁目にて確認)
表層改良を2m程度行った家屋の被害の程度は少ないが、隣接する未対策の家屋の被害は甚大であった。(表土に山砂分多い)
③ 地下水位低下工法
地下水位が高く、表土に砂分が多い地盤では 液状化被害が甚大となった。
地下水位を下げると地上に被害を及ぼす液状化の発生の程度を減ずることが可能となる。
ただし、ウェルポイントやディープウェルなどの工法の採用により、既設構造物に被害を与えた例は数多く発生している。(軟弱シルト層の圧密や緩い砂の側方流動、水を抜いた事自体による体積の縮小等による)
よって、弊社では構造物直下のセメント系薬液注入や建換え時の表層改良の併用を弊社ではお勧めします。(セメント系薬液の注入厚や注入量、表層改良厚は増やす必要がある。)
弊社の地盤改良併用家屋傾き修正工法(ハイブリッド工法)は 埋立層(深度7m程度)からの地盤改良を行っているため、道路で地下水位低下工法を行っても、不等(不同)沈下をしないように工事を行っております。
これが、道路と家屋の液状化対策一体化工法(真の液状化対策工法)であると考えているからです。
全てでは無いですが、様々な論文から既存建物がある場合の液状化対策における有用な手段をざっとまとめてみると
① セメント系薬液注入(先の2度に渡る中越沖地震においても効果が確認されている。)
② 3m厚程度の表層改良
③ 地下水位低下工法(セメント系薬液注入または3m厚程度の表層改良との併用)
現在の技術で対応が可能と思われるものは以上のようなものとなります。(他にもあると思いますが) 私が昨年より申し上げている内容が、第三者により、理論や解析結果や事実として発表されております。
① セメント系薬液注入
対象地盤の体積比7%以上の注入により、水の流れやすさを1/10~1/100にすることができる。(液状化に伴う、噴水や噴砂量を劇的に改善することが可能)
主な理由: 浸透しにくい材料の使用、土粒子の骨格の変化、密度の増加等による
② 3m厚程度の表層改良(レベル1程度の地震の場合)
表層3m程度の非液状化層の形成により、その下で液状化しても地上に影響を与えにくい。
被害の大きい家屋ほど、表層の盛土に山砂分が多い土を用いている場合が多い。
(舞浜3丁目、弁天1丁目、美浜3丁目にて確認)
表層改良を2m程度行った家屋の被害の程度は少ないが、隣接する未対策の家屋の被害は甚大であった。(表土に山砂分多い)
③ 地下水位低下工法
地下水位が高く、表土に砂分が多い地盤では 液状化被害が甚大となった。
地下水位を下げると地上に被害を及ぼす液状化の発生の程度を減ずることが可能となる。
ただし、ウェルポイントやディープウェルなどの工法の採用により、既設構造物に被害を与えた例は数多く発生している。(軟弱シルト層の圧密や緩い砂の側方流動、水を抜いた事自体による体積の縮小等による)
よって、弊社では構造物直下のセメント系薬液注入や建換え時の表層改良の併用を弊社ではお勧めします。(セメント系薬液の注入厚や注入量、表層改良厚は増やす必要がある。)
弊社の地盤改良併用家屋傾き修正工法(ハイブリッド工法)は 埋立層(深度7m程度)からの地盤改良を行っているため、道路で地下水位低下工法を行っても、不等(不同)沈下をしないように工事を行っております。
これが、道路と家屋の液状化対策一体化工法(真の液状化対策工法)であると考えているからです。